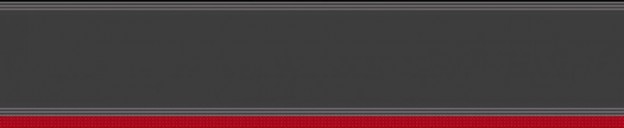『山県有朋』(伊藤之雄著・文春新書)
 山県有朋は明治の元勲として、陸軍・内務官僚を作り上げた長州藩のドンだが、イメージは暗く、陰険で「権力」に固執。本の帯には「不人気なのに権力を持ち続けたその秘訣とは?」。当時のマスコミにも人気がなかった。著者(京都大学教授―日本近代政治史)は、好きでなかった山県と伊藤博文、井上馨、桂太郎らとの手紙のやりとりの研究を通じて、「猜疑心が強く暗い性格」の奥に、愚直ともいえる生真面目で優しい山県を発見し、どんどん好きになっていったという。本書は生涯(天保9年―1838年から大正11年―1922年)を通じての時代史だが、やはりこの時代は明治維新(戦争)、西南戦争、日清・日露戦争、第一次世界大戦等、甲対乙といった水面上のエネルギーのぶつかり合い(そしてそれは必ず財政難との戦いでもある)と、明治国家樹立、憲法制定、議会開設、条約改正、政党政治といった体制構築の為のエネルギー投下、そしてやはり底辺には人間m、感情の理屈を超えた、そして仕方のない接触と離反、友情と憎悪が繰り返される。
山県有朋は明治の元勲として、陸軍・内務官僚を作り上げた長州藩のドンだが、イメージは暗く、陰険で「権力」に固執。本の帯には「不人気なのに権力を持ち続けたその秘訣とは?」。当時のマスコミにも人気がなかった。著者(京都大学教授―日本近代政治史)は、好きでなかった山県と伊藤博文、井上馨、桂太郎らとの手紙のやりとりの研究を通じて、「猜疑心が強く暗い性格」の奥に、愚直ともいえる生真面目で優しい山県を発見し、どんどん好きになっていったという。本書は生涯(天保9年―1838年から大正11年―1922年)を通じての時代史だが、やはりこの時代は明治維新(戦争)、西南戦争、日清・日露戦争、第一次世界大戦等、甲対乙といった水面上のエネルギーのぶつかり合い(そしてそれは必ず財政難との戦いでもある)と、明治国家樹立、憲法制定、議会開設、条約改正、政党政治といった体制構築の為のエネルギー投下、そしてやはり底辺には人間m、感情の理屈を超えた、そして仕方のない接触と離反、友情と憎悪が繰り返される。
政治が判断と行動力を必然とするならば、この時代の指導者はその前提となる情報が今より遥かに劣っていた。特に、山県はその中でも劣っていた。しかし、明治政府の指導者達の殆どはすさまじい内戦を戦い、生き残った人々だ。吉田松陰、高杉晋作、坂本龍馬等は既にいない。つまり、旧幕府側を含めて勝者の集まりであり、既に判断力の優れたエリートたちなのだ。山県は何回も判断ミス又は優柔不断を繰り返し、失脚の瀬戸際に追い込まれるが生き残る。その原因は、西郷や大久保、伊藤や井上といった「勝ち組」が山県をいつも助けてくれるからだという。それだけ山県は好かれているのだ。
山県は徹頭徹尾、政党政治を嫌った。だから伊藤とは合わない。しかし、年下だが格上の伊藤にいつも助けられる。政党政治―大衆政治の権化の様な西園寺や原敬を徹底的に排除しようとしたが、晩年彼らを評価する。逆に子分ナンバーワインの桂太郎を首相就任前後から敵視し排除しようとし、没後、国葬にも反対する。人間のぶつかり合いは歴史として面白い。しかし、当事者は必死だ。石部金吉の様な努力家、つきあってもつまらなそうな山県の奥にある人柄が危機を救った訳だが、対外政策は以外にも柔軟だ。
清・英・仏・露・米との関係は軍のトップでありながら慎重だ。陸軍の最高指導者なのに、対華21カ条要求やシベリア出兵も慎重に考えている。その要因は庭作りや漢詩、謡曲といった多趣味もあるという。しかし現実は必ずしもそうならない。時代の勢いが良くも悪くも決定する。
私の友人が「今は攘導攘夷の時代の様だ」と言ったことがある。様々な報道や意見があるが、マスコミとネットは必ずしもイコールではない。とにかく、理屈抜きのムードで世の中が一方的に流れてゆく。何でもありの世の中だ。世界史的に見ても、宗教裁判、マッカーシズム、文化大革命、そしてマスコミ至上権力の場当たり的享楽、平和主義等々が人間の歴史の長い部分を占めている。
著者の思いは別にして(好き嫌いは別にして)、国家の主役の一人だった人物の評価が没後から定着し、「悪や陰の代表」の様なイメージが定着してしまった。著者は「歴史の評価は必ずしも常識とは限らない」と訴えている。これも歴史学者の良心だろう。だから歴史は面白いし、その評価は当人にとっては恐ろしい。